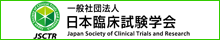THERAPEUTIC RESEARCH On-line

左:河野雄平氏,右:今井潤氏
2011年日本高血圧学会学術集会の最終日となった10月22日,パネルディスカッション「血圧変動性の新たな視点」(座長:今井潤氏 東北大学,河野雄平氏 国立循環器病研究センター)が行われた。血圧変動性は今学会でとくに注目されたテーマであり,HOMED-BPをはじめ家庭血圧測定についての研究も数多く発表された。本パネルディスカッションでは,外国人パネリスト1名を含む計6名のパネリストが,それぞれの視点から血圧変動性の重要性を述べた。

Peter M Rothwell氏
脳卒中と高血圧についての研究で,世界の第一人者として活躍しているPeter M Rothwell氏(オックスフォード大学臨床神経学教授)は,血圧変動性と脳卒中リスクが強く相関し,さらに降圧薬の脳卒中予防効果は,服用中の血圧変動性と強い相関を示すことを紹介した。同氏は近年,血圧変動性に関する論文をLancet誌を中心に数多く発表し,この研究領域を牽引している1人である。
同氏らが実施したUK-TIA試験のデータを,血圧変動性の観点で再解析した結果,試験開始後7回の血圧測定値をもとに算出した収縮期血圧(SBP)の標準偏差は,脳卒中発症リスクとの相関が認められ,標準偏差の十分位でみたときに,その最大群は最小群にくらべ約10倍の脳卒中発症リスクを有することが示された。これは平均SBPで補正後のデータであり,SBPレベルにかかわらず測定日によるばらつきが脳卒中発症リスクに強く影響することを示している。
Staessenらのメタ解析で示されたように,これまで降圧薬の有用性,とくに脳卒中予防においては,たとえわずかであっても降圧度の差に依存すると考えられてきた。しかし,Rothwell氏は,降圧度の差よりも血圧変動性の差が重要である可能性を指摘している。その根拠となったのは,Ca拮抗薬とその他の降圧薬を比較した大規模ランダム化比較試験(VALUE,ALLHAT,CAMELOTなどの6試験)を統合したデータである(Rothwell PM. Lancet. 2010; 375: 938-48. PubMed)。試験期間中のSBP平均値に大きな群間差はないものの,その標準偏差と脳卒中発症リスクはCa拮抗薬群のほうが小さいことが示された。この集団におけるSBP標準偏差は個人のSBP標準偏差と強い相関があり,集団でみた個人間のばらつきは,個人内の血圧変動を反映するものであることが確認されている。
さらに,Rothwell氏らが実施したメタアナリシスでは,Ca拮抗薬と利尿薬は他の降圧薬に比べ,(1)追跡期間中のSBP分散比,(2)ベースライン時からのSBP変動係数ともに有意に少なかったが,ARB,ACE阻害薬,β遮断薬は有意に大きいことが示された(Webb AJ, et al. Lancet. 2010; 375: 906-15. PubMed)。
では,降圧薬の有用性を評価する際,降圧度と分散のどちらを重視すべきなのだろうか。Rothwell氏らの解析では,プラセボ比較の場合,全脳卒中のオッズ比は,降圧度との相関は示されたが,分散比との相関は示されなかった。一方,降圧薬同士の比較の場合は正反対の結果が得られ,降圧度との相関は示されず,分散比との相関のみが示された。Rothwell氏は,「このデータは,プラセボ比較では降圧度,降圧薬同士の比較では分散を重視すべきことを示唆している」と述べた。

甲斐久史氏
久留米大学心臓血管内科の甲斐久史氏は,血圧変動性の縮小を超えたARBの新たな可能性について述べた。
血圧変動の大きい症例では標的臓器障害が進行することが知られている。そのメカニズムには,交感神経系や血管スティフネス,レニン-アンジオテンシン系などのほか,天候などの環境要因が関与するといわれるものの,詳細は不明である。同氏らは,高血圧自然発症ラット(SHR)に洞大動脈除神経(sino-aortic denervation: SAD)術を施行することで,平均血圧は変わらないが血圧変動が大きくなる「血圧変動高血圧ラットモデル」を新たに確立し,メカニズムの解明を進めている。その結果,通常のSHRにくらべ,血圧変動高血圧ラットモデルでは心筋線維化がさらに亢進し,顕著な心肥大が引き起こされることが示された。
また,血圧変動高血圧ラットでは,通常のSHRや血圧変動正常血圧ラットにくらべ,マクロファージの浸潤や炎症マーカーの上昇,さらにアンジオテンシンII(AII)発現量の上昇が認められた。そこで,血圧を下げない程度のAII受容体拮抗薬(ARB)を投与すると,血圧変動性の縮小は認められないものの,心筋線維化や心肥大の亢進のほか,マクロファージの浸潤や炎症マーカーの上昇も抑制されることが示された。
同氏は,「血圧変動性によって引き起こされる持続的な炎症反応は,AIIの遮断によって抑制され,それによって標的臓器障害が抑制されるのではないか」と考察している。そのうえで,ARBの有用性について3つの観点からまとめた。すなわち,1つ目が降圧効果,2つ目が降圧を超えた効果,3つ目が血圧変動の縮小を超えた効果,である。

田村功一氏
横浜市立大学大学院医学研究科病態制御内科学の田村功一氏は,慢性腎臓病(CKD)合併高血圧においても血圧変動性を考慮した降圧療法が重要であると述べ,とくに自由行動下血圧(ABPM)で測定する短期変動性が新たな治療標的になり得ることを指摘した。
CKD合併高血圧患者のなかでも冠動脈疾患を有する症例では,血圧短期変動性が昼間・夜間ともに増大する。このことから田村氏らの研究グループは,心腎連関に対する血圧短期変動性の関与に注目した研究を進めてきた。それによると,血液透析中の症例において,アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)群と非ARB群でABPMのデータを比較すると,6ヵ月後・12ヵ月後の血圧は同等であったが,夜間における血圧短期変動性はARB群のほうが有意に少ないことが示された。同時に,心リモデリングやBNP,酸化ストレスの指標などもARB群で有意に低く,多変量解析では夜間のSBP短期変動性の短縮が,心肥大の退縮に有意に相関していた。
一方,近年,患者数が増加している糖尿病性腎症においては,テルミサルタンはロサルタンよりも,尿蛋白/クレアチニン比の減少,心血管イベントの抑制をもたらすことがAMADEO試験で明らかにされている。田村氏らは,両薬の有用性の差に血圧短期変動性が関与した可能性を考え,糖尿病性顕性腎症患者を対象としたテルミサルタンとロサルタンのクロスオーバー試験を行い,血圧短期変動性に与える影響を比較した。その結果,投与12週間後における夜間のSBPはテルミサルタン群はロサルタン群に比べ有意に低かったが,その他のABPM測定値に有意な群間差は認められなかった。一方,血圧短期変動性(昼間・夜間ともに),尿中蛋白排泄量はテルミサルタン群はロサルタン群よりも有意に少なかった。多変量解析では,尿中蛋白排泄量の減少には,夜間のSBPのほか,24時間にわたるSBPの血圧短期変動が有意に相関することが示されている。
以上を踏まえ,田村氏は「血圧短期変動性は心腎連関に関与していると考えられ,血圧短期変動性はCKD合併高血圧の治療標的となりうる可能性がある」と述べた。

大石充氏
大阪大学老年・腎臓内科学の大石充氏は,血圧変動性と血管トーヌスの関係を腎内血管抵抗を用いて証明し,疫学研究のデータから示唆される血管変動性の新たなメカニズムについて紹介した。
本セッションの冒頭でRothwell氏らが述べたように,受診ごとの血圧変動性が大きいほど脳卒中リスクが上昇する。Ca拮抗薬ベース治療はβ遮断薬ベース治療よりも心血管イベント抑制効果が高いことを示したASCOT-BPLA試験では,Ca拮抗薬ベース治療のほうが血圧変動性が少ないことが報告された。メタ解析の結果でも,血圧変動性は,交感神経に直接作用するβ遮断薬やα遮断薬ではなく,Ca拮抗薬によって縮小されることが明らかにされている。このため大石氏は,交感神経系ではなく,Ca拮抗薬の作用機序の1つである血管トーヌスの改善が,血圧変動性の縮小に関与すると考え,腎血管抵抗指数(RI)と血圧変動性の関係を検討した。この結果,RIと血圧の相関は見られず,収縮期血圧(SBP)の標準偏差もしくは変動係数が大きいとRIが高いことが示された。
さらに,同氏らが行ったNOAH研究でも興味深い結果が得られている。大阪大学医学部附属病院に通院した本態性高血圧患者813例を平均7.0±3.0年追跡すると,SBPの標準偏差が高値の症例で左室心筋重要係数やプラークスコア,脈波伝播速度が高いことが明らかとなった。

大久保孝義氏
滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門の大久保孝義氏は,高血圧診断・予防・治療における各種測定法の血圧値およびその変動性の意義について,現時点で得られているエビデンスをまとめた。
現在,血圧測定には(1)診察室血圧,(2)自由行動下血圧,(3)家庭血圧の3つの方法がある。診察室血圧は,心血管リスクの検出に有用であり,治療ターゲットとしての有用性も数多くの臨床試験によって証明されている。一方,自由行動下血圧は,心血管リスクの検出には有用であるものの,治療ターゲットとなり得るかは不明である。IDACOプロジェクトによると,自由行動下血圧値のなかでもとくに,心血管イベントの独立した寄与因子となったのは,未治療患者では昼間・夜間の双方であったが,治療中患者では夜間のみであり,昼間の血圧は心血管イベントリスクにまったく影響しないという興味深いデータが得られている。また家庭血圧については,朝+晩および朝と晩のそれぞれが心血管リスクの検出に有用であり,HOMED-BP研究の結果から治療ターゲットとしての有用性も示唆されている。
では,血圧変動性についてはどうであろうか。診察室血圧から得られる診療ごとの血圧の変動性など,自由行動下血圧から得られる昼間と夜間の血圧差,モーニングサージ,測定ごとの変動性,さらに家庭血圧から得られる日々の血圧変動は,いずれも心血管リスクの評価に有用であることが示されているが,治療ターゲットとしての妥当性は証明されていない。
同氏は,「測定法にかかわらず血圧値は心血管リスクの評価に有用であり,診察室血圧のみならず家庭血圧も治療ターゲットになり得る可能性が高い」とまとめた。さらに,血圧変動性は心血管リスクとの関連を示すものの,治療ターゲットとしての妥当性を示すエビデンスは現時点で存在しないことを指摘した。