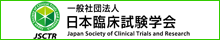THERAPEUTIC RESEARCH On-line
| CORE320 | Diagnostic Performance of Combined Noninvasive Coronary Angiography and Myocardial Perfusion Imaging Using 320-row Detector Computed Tomography : The CORE320 Multicenter, Multinational Study |
|---|
| ‣エキスパートインタビューを読む: | 最先端デバイスを使いこなすために,診断方法の簡略化・標準化が求められる |

João A.C. Lima氏 |
試験背景/目的 狭心症や心筋梗塞の診断には,従来,カテーテルX線造影(侵襲的冠動脈造影:ICA)による冠動脈の狭窄評価と,単一光子放射断層撮影(SPECT)による心筋虚血の評価が実施されてきた。近年CTによる診断も行われるようになっているが,これまでのCTによる撮像範囲は64列面CTで約4 cm,256列面CTでも約10 cmであり,心臓(冠動脈)検査を行う場合は,螺旋状にスキャンして撮影した画像をつなぎ合わせて解析する必要があった。
「Aquilion One™(2007年発売,東芝メディカルシステム社製)」は1回の非侵襲的検査でCT血管造影(CTA)+CT還流イメージング(CTP)が可能な世界初の320列面CTで,1回のスキャンで心臓が丸ごと収まる16 cmの範囲が撮像可能となった。これまでのように,部分画像をつなぎ合わせることによる画像精度の劣化がなくなるほか,撮影時間が短くなるため,被曝線量,造影剤量も少なくなる。
CORE320は320列面CTによる冠動脈狭窄および心筋還流異常の診断確度を,ICA+SPECTと比較する国際多施設合同第III相試験である。8月28日,Hot Line 3においてprincipal investigatorのJoão A.C. Lima氏(Johns Hopkins Hospital,米国)より試験結果が発表された。
試験プロトコール 対象は冠動脈疾患またはその疑いのために,60日以内に従来の侵襲的冠動脈造影を実施するように紹介されてきた患者で,全例ともに4種類(CTA,負荷CTP,SPECT,ICA)の画像撮影を実施。研究者,治療にあたる医師,患者は盲検化されており,すべての画像は中央研究所で解析された。
一次エンドポイントはCTA+CTPによる冠動脈狭窄および心筋還流異常の診断確度についての,(1) ICA+SPECTとの比較,および(2) ICAのみとの比較。
試験結果 対象は8ヵ国の16施設から登録された45~85歳の381例。年齢は62歳(中央値)で男性が66%,BMIが27kg/m²(中央値)。高血圧が78%,糖尿病が34%,脂質異常症が68%,Agatstonカルシウムスコアが162(中央値)で,心筋梗塞既往例が25%,PCI施行例が29%だった。
対象のうち,閉塞性冠動脈疾患と診断された患者はICAで59%,ICA+SPECTで38%であった。
ICA+SPECTによる冠動脈狭窄率≧50%の診断をreference standardとしたとき,CTA+CTPによる血流異常診断の感度・特異度についてのROC曲線下面積(AUC)は0.87(95%信頼区間0.83~0.91)だった。なお,CTA+CTPは,CTAに比べてAUCが有意に大きかった(0.87 vs 0.81,P<0.001)。さらに,冠動脈疾患既往例を除外すると,CTA+CTPのAUCは0.93(95%信頼区間0.89~0.96)となった。
30日後まで血行再建術施行をreference standardとしたとき,その予測感度・特異度についてのAUCはCTA+CTPで0.79(95%信頼区間0.76~0.83),ICA+SPECTで0.81(95%信頼区間0.78~0.84)となり,両者に有意差は認められなかった(P=0.35)。
Lima氏は「CTAに加えてCTPを実施することにより,血流が低下した狭窄部位の診断能は向上し,それはICA+SPECTに匹敵することが証明された。CTA+CTPを非侵襲的な一度の検査で実施できることは非常に有益である」と述べた。