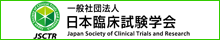THERAPEUTIC RESEARCH On-line
2010年8月28日–9月1日,ストックホルム(スウェーデン)において,欧州心臓病学会(ESC)学術集会が開催された。今後の臨床に影響を与えうるトライアルを取り上げたスペシャルセッション「Hot Line」では,抗血栓療法に関する臨床試験が数多く取り上げられ注目を集めた。
ここでは,J–LANCELOT試験の試験責任者を務め,わが国の血栓症研究をリードする東海大学の後藤信哉氏に,ESC発表トライアルについて解説してもらった。
ESC参加者数は毎年増加しており,従来はAHA/ACCで発表されていたようなメガトライアルも,最近はESCで多く発表されるようになった。今回も抗血栓療法について多くの重要な試験が発表された。認可承認試験ではないため注目度は低いが,実臨床の観点からみると,高リスク心房細動(AF)患者において経口第Xa因子阻害薬apixabanとアスピリンを比較したAVERROES試験の意義は際立って大きい。
各国の診療ガイドラインは,AF症例に対しINR 2–3のワルファリン介入を推奨しているが,実際に患者の出血イベントと向き合う臨床医の多くは,推奨に従った介入を行っていない。予防介入では安全性を重視すべきとの視点でも,「効果も少ないが副作用も少ないアスピリン」を使用しがちな実態は理解できる。
しかし,薬剤の認可承認や規制を行うことを目的にするのであれば,AF症例に対する新規の抗血栓薬は,すでに有効性と安全性の確立された「標準治療」であるワルファリンとの比較において行われるべきとの論理が正当である。その意味では,AVERROES試験は「標準治療」と比較した試験ではない。
ランダム化比較試験は「患者集団」に対する科学である。「リスク因子を有するAF症例」という集団では,「INR 2–3のワルファリン介入」の有効性・安全性は,その他の介入に優ることは事実と認識すべきである。しかし,個別の患者を対象として治療している臨床医の視点では,安全性がより重視される場合も多い。AVERROES試験は,「標準治療」ではなく「実臨床での治療」であるアスピリンとの比較において,経口第Xa因子阻害薬が有用性を示したとの点で価値が大きいと筆者は考える。
本稿執筆の数日前に,米国食品医薬品局(FDA)が経口抗トロンビン薬dabigatran 150mgの非弁膜症性AF患者に対する脳卒中および全身性塞栓症の予防適応を認可承認することが発表された。経口抗凝固薬としては実質的にワルファリン以外に選択肢がないという時代は終わろうとしている。認可承認に際し根拠となったdabigatranとワルファリンの有効性,安全性を検証したRE–LY試験は,二重盲検ではなくオープンラベルにて実施された。従来,一般的にバイアスのかかるオープンラベルの試験の結果をもとに,心血管領域の重要な薬剤が認可承認されることはなかった。高齢化とともに増加するAF,AFに合併する重篤な脳卒中,その後の長期にわたるQOL低下という現実と,AF症例における脳卒中予防に使用されているワルファリンが個人差,併用薬,食事などの影響を強く受けるという現実が,多少の無理を通した認可承認につながったのかもしれない。
今回の AVERROES試験 は,ワルファリン不適応のAF患者において,新規抗凝固薬apixabanがアスピリンにくらべ,脳卒中+全身性塞栓症イベントを有意に抑制することを示した。重要なことに,出血性合併症発生率についてはapixabanとアスピリンで有意差が認められていない。apixabanの出血リスクがアスピリン並みとなれば,将来はAF症例にあえてアスピリンを使用する根拠もなくなる可能性がある。さらに,おなじ第Xa因子阻害薬であるrivaroxabanやedoxabanの開発も進んでおり,これらが抗凝固薬に対する基本的な考え方を大きく変える可能性もある。今後の動向を十分に見極める必要がある。
繰り返しになるが,Evidence-Based Medicineの観点では,リスク因子を有するAF患者の血栓イベント発症予防には,ワルファリンを使用すべきである。しかし,一部の症例ではワルファリンによる管理が極めて困難で,その理由はCYP2C9の遺伝子多型,特異な食生活(日本でいえば納豆の嗜好),併用薬など多岐にわたる。さらに,ワルファリンの服用により頭蓋内出血を含む重篤な出血性合併症のリスクは増加するため,出血リスクを受け入れられない症例もワルファリンの不適応症例となる。実際に「薬剤溶出ステントを留置し,抗血小板併用療法を長期に継続している」「前立腺がんのホルモン治療中で出血リスクがある」などの理由により,ワルファリンを使用できない症例は極めて多い。本試験は,医薬品の規制や認可承認の際に望まれる「標準治療を対照とした試験」ではないが,本試験の対象と同様のバックグラウンドをもつ患者は,実臨床で多数存在するものと推測される。したがって,本試験の対象者は実臨床に近い対象であると筆者は理解している。AVERROES試験は製薬企業や規制当局よりも,実臨床を担う臨床医にとって価値の高い臨床試験であった。
apixabanは,経口投与可能な選択的第Xa因子阻害薬である。服用後の効果発現は早く,半減期も約12時間である。症例ごと,あるいは症例のおかれた環境ごとの効果のばらつきが少ないため,モニタリングは不要である。RE–LY試験の結果をもとに米国にて認可承認がなされたdabigatran(150mg/日)は,凝固カスケードの最下流にあるトロンビンの阻害薬である。トロンビンより上流に位置する活性化凝固第X因子の阻害(apixaban)と,トロンビンの阻害(dabigatran)に,有効性・安全性に違いがあるのかについては,今後の検討課題である。
ところで,抗血小板薬と抗凝固薬の違いがしばしば取り上げられるが,臨床的な有効性や安全性にどのような違いがあるのだろうか。
現在の実臨床において使用されている抗凝固薬の代表選手はワルファリン,抗血小板薬の代表選手はアスピリンやクロピドグレルである。人体にできるすべての血栓は,血小板とフィブリン,炎症細胞の混合血栓であるため,血栓の形成メカニズムを精緻に阻害するのであれば,抗凝固薬,抗血小板薬ともに血栓性疾患に有効性を発揮すると想定される。しかし現状の「抗血小板薬=アスピリン」,「抗凝固薬=ワルファリン」として比較すると,心筋梗塞再発予防であってもAF時の血栓塞栓症予防であっても,抗凝固薬の有効性は抗血小板薬を上回る。
従来型のワルファリンは,凝固カスケードの中心に位置する血液凝固第II,VII,IX,X因子を阻害し,その強力な抗凝固作用ゆえに出血性合併症が多いという欠点を有する。一方,今回のAVERROES試験で検討したapixabanは,活性化第X因子を選択的に阻害する抗凝固薬である。その出血性合併症発生率には,アスピリンとの有意差が認められていないことから,apixabanによる出血リスクはワルファリンよりも小さいと推測される。
生体内においては,抗凝固薬と抗血小板薬がまったく別々の系に作用しているのではなく,「抗凝固薬」であっても,血小板活性化を阻害し,血小板上の凝固系活性化やトロンビン産生を阻害する。血小板にはトロンビン受容体が存在するため,トロンビン産生阻害は抗凝固作用であるとともに抗血小板作用でもある。血小板と凝固系の相互作用による血栓形成のポジティブフィードバックを断ち切るとの視点が重要である。
rivaroxabanは,apixabanと同様,経口投与可能な選択的第Xa因子阻害薬である。服用後の効果発現は早く,一日一回の服薬で足る。症例ごと,あるいは症例のおかれた環境ごとの効果のばらつきが少ないため,apixabanと同様にモニタリングは不要である。長らくワルファリンのみの選択肢の時代が続いたが,急速に経口抗凝固薬の選択肢が増加する時代は目前に迫っているのが世界の現状であろう。
EINSTEIN DVT試験では,肺塞栓症(PE)を認めない症候性深部静脈血栓(DVT)患者において,rivaroxabanの症候性静脈血栓塞栓再発抑制効果はエノキサパリン/ビタミンK拮抗薬(VKA)に劣らないことが示された。
ワルファリンは素人に難しいばかりでなく,玄人にも奥の深い薬剤である。至適INRは個人ごとに,場合によっては個人のおかれた環境ごとに異なる可能性があり,治療を標準化することは難しく,ばらつきのない効果を得ることも難しい。臨床試験では本来,薬効がばらつかない「標準化された治療」どうしの比較において行われるべきであるが,ワルファリンを比較対照とする以上,「効果の標準化されたrivaroxaban」対「INRを用いて効果を標準化しようと努力したワルファリン」の比較になるのはやむを得ないことであろう。
EINSTEIN DVT試験のエノキサパリン/VKA群では,INR 2–3にコントロールできた対象は57.7%であった。INRを2−3にコントロールすることが,個々の症例にとって本当に至適であるか否かは別として,標準化しようと努力はしたけれども十分に標準化できなかった点を批判されることはやむを得ない。
血栓イベントの多くは急性期におこる。EINSTEIN DVT試験の追跡期間は1年と設定されたが,Kaplan−Meier曲線ではほとんどのイベントは3ヵ月以内に起こっていることが示された。長期間にわたって追跡することは,投薬期間を考えるうえで重要であり,薬剤の認可承認時にも重視される。本試験の結果は,臨床的には急性期の再発予防こそが主要な治療標的であることを示唆している。
わが国では,PCI施行時の抗血栓薬の選択肢は限られている。多くの場合,未分画ヘパリンによる抗凝固療法が施行され,アスピリン,チクロピジン/クロピドグレルなどの抗血小板薬が併用される。日本人はもともとの血栓発生リスクが低いためか,未分画ヘパリンをさほど厳格に使用しなくても,実態としては,血栓イベント・出血イベントともに問題とならない症例がほとんどである。まれにPCI施行中に血栓イベントが多発する症例もあり,その場合は経静脈的抗血小板薬によるメリットが想定されるが,それらを除けば新しい抗血栓薬の必要性を感じないという臨床医が多数派であろう。
諸外国には,未分画ヘパリン以外の経静脈的抗凝固薬,わが国では承認されていない経静脈的抗血小板薬など,複数の選択肢がある。PCI施行中の血栓イベント,出血イベントともに日本人と比較して発生率が高いために,新しい薬剤を必要としているのであろう。われわれ日本の臨床医には,欧米の医師が感じている(と想定される?)新規抗血栓薬の必要性が実感できない。
今回のESCではPCI施行時における抗血栓療法についての4試験の結果が発表された。最近の抗凝固薬,抗血小板薬に関する検討は流行となっているが,基本的な作用メカニズムに新規性のある薬剤は少ない。似たような薬剤の効果を比較しても新味は乏しい。
ISAR–REACT 3A試験では,基本治療としての未分画へパリンの用量が検討された。わが国における未分画ヘパリン投与量の実態は,本試験にて低用量とされた100U/kgよりもさらに低用量であると想定される。本試験では,われわれにとっては比較的高用量である100U/kgが,欧米の通常用量である140U/kgと比較され,100U/kgの非劣性が示されたに過ぎない。われわれからすれば,「いまさらなにを」という試験であった。
未分画へパリンの作用には個人差があり,投与中に用量調節が必要であるため,欧米では一定の投与量にて一定の有効性が期待される低分子へパリンも広く使用されている。ただ未分画へパリンと低分子ヘパリンの作用機序は基本的に同一であるため,両者は使い勝手には差があるとしても,両者の有効性や安全性を比較することの意味は乏しい。この意味の乏しい試験としてATOLL試験が行われた。なんでも大規模臨床試験をすればよいというものではない。
FUTURA OASIS 8試験も,ヘパリンの抗凝固機能部位を合成したフォンダパリヌクスを基礎治療薬として,その後の未分画へパリン追加の有効性と安全性,そして至適用量について検証した試験であるが,プロトコールが複雑で,われわれのように未分画へパリンで不足を感じていない国の医師からみると,なにを目的とした試験であるのか明瞭でない。さまざまな抗凝固薬のオプションがあっても,現在の未分画へパリンにて実質的には困ることがないというのが本当のところなのであろう。
抗血小板薬としてはアスピリン/クロピドグレルが標準治療の地位を確立している。さらにprasugrelもすでに多くの国にて使用されており,ticagrelorも承認が近いとみられる。このようななかで,経静脈・経口のいずれでも使用できる薬剤としてelinogrelが開発され,今回のESCでは第II相試験であるINNOVATE–PCI試験の結果が発表された。第III相試験への移行における安全性の検証を主眼とする試験で,120日間の追跡において,クロピドグレルとほぼ同等の安全性と有効性が認められた。
われわれは,日本人の急性冠症候群(ACS)患者,高リスク冠動脈疾患(CAD)患者を対象にした,新しい機序をもつ抗血栓薬atopaxar(E5555)に関する第II相試験J–LANCELOTを実施し,その結果を今回のESC2010にて発表した。atopaxarは,プロテアーゼ活性化受容体1(PAR–1)に拮抗し,血小板活性化を阻害する機序をもつ抗血小板薬である。J–LANCELOTでは,標準治療へのatopaxarの上乗せ投与と,標準治療のみ(プラセボ)を比較した結果,ACS患者,高リスクCAD患者のいずれにおいても,atopaxarが出血イベントの増加を伴わずに主要有害心血管イベントを抑制する可能性が示唆された。
同様の機序の薬剤としてvorapaxarの試験が先行しており,われわれの発表はvorapaxarの過去の試験と相同であった。
血小板上には複数のトロンビン受容体が存在するが,PAR(Protease Activated Receptor)と総称される受容体は,蛋白分解酵素であるトロンビンの作用により受容体自体が分解され,分解された受容体の一部がリガンドとして作用する受容体である。トロンビンは強力な血小板活性化物質であるため,トロンビン受容体を阻害すると重篤な出血性合併症が発症することが想定されたが,マウスのトロンビン受容体をノックアウトしても,出血時間の著しい延長は認められなかった。トロンビン受容体の阻害が血小板の活性化と凝集を抑制しながら,出血性合併症を増加させないメカニズムについてはいくつか議論があるものの,現時点では正確なメカニズムは不詳である。
ベースライン時の投薬状況をみると,ACSではチエノピリジン系薬剤が90%以上,アスピリンは100%近く投与され,CADではそれぞれ40%前後,100%近くが投与された。
ACSでは冠動脈内局所の血栓性の更新も認められるため,アスピリン/クロピドグレルの併用療法も多くの場合に必須である。一度併用をはじめた症例では,抗血小板薬の中止時に血栓イベントが起こると験(ゲン)が悪い。医療経済的にも抗血小板薬中止のインセンティブの働きにくいわが国では,安定期のCAD患者でも40%で基礎治療のアスピリンに加えてチエノピリジンが併用されており,これは日本特有の医療実態を反映していると考えられる。
つまり,本試験参加者の多くは,ただでさえ強力なアスピリン/クロピドグレルの併用療法に加えてatopaxarが上乗せ投与され,さらにACS患者ではatopaxar 400mgのローディングが行われた。本試験のプロトコールは,ランダム化ののちにローディングを行うものであり,大多数の症例が冠動脈インターベンション治療を受けているため,出血リスクとなるインターベンションの前後にも強力な抗血小板介入が行われていたことになる。それにもかかわらず重篤な出血イベントが決して多く発生しなかった要因としては,わが国では一般的に抗凝固薬としてのヘパリンの使用量が欧米よりも少ないこと,GPIIb/IIIa受容体阻害薬のような強力な経静脈的抗血小板薬が投与されていないこと,さらに,日本の医師が注意深く治療を行っていること,日本人患者は一般的に医師の指導内容を遵守するよい患者であることなどが考えられる。
J–LANCELOTでは,トロンビンによって惹起される血小板活性化の指標として,トロンビン受容体刺激ペプチドによる血小板凝集率を計測した。今回の試験で用いた最少用量以上の用量では,血小板凝集はほぼ完全に阻害されることが示された。すなわち,最少用量以上の用量にて,atopaxarがもつ薬理的作用が十分に発揮されると考えられる。
しかし,この薬理的作用の程度は臨床的有用性に直結するものではない。実際に,J–LANCELOT試験で血栓イベントが完全に予防されたわけではなく,また出血性合併症が著しく増加したわけでもない。血小板凝集の計測は,薬剤の薬理的作用の目安にはなるが,臨床的有用性の目安として用いることは適切ではない。
血小板凝集機能検査は本来,出血性疾患のスクリーニングを目的とした血小板機能検査法として使用されてきた。近年の臨床試験をみると,クロピドグレルなどの抗血小板薬の薬効予測を目的としてこの血小板凝集機能検査が用いられているようだが,これはおそらくほとんど意味をなさないといえよう。クロピドグレルは複数のアデノシン二リン酸(ADP)受容体のうちP2Y12を選択的に阻害する薬剤である。クロピドグレルによるADP惹起血小板凝集の抑制効果には個人差があるが,イベント抑制効果との相関は明確ではない。複数あるADP受容体のうちP2Y12のみを完全に阻害しても,ADP惹起血小板凝集率には個人差がある。一方,トロンビン受容体については,やはりPAR–1,PAR–4など複数存在するが,ヒトではPAR–1の役割が大きいことが知られている。しかし,ADPであろうとトロンビン受容体活性化ペプチドであろうと,血小板凝集計測によって心血管イベント,出血イベントを予測する価値は大きいとはいえない。
抗血小板薬の効果と遺伝子多型の相関については,2つの結果が発表された。CURE Genetics試験とACTIVE Genetics試験の統合解析では,CYP2C19の遺伝子多型はクロピドグレルの効果に影響を及ぼさないこと,PLATO genetic substudyでは,CYP2C19やABCB1の遺伝子多型に関わらずticagrelorはクロピドグレルよりも有用であることが示された。しかし,そもそもCYP2C19遺伝子多型とクロピドグレルの薬効発現について検討することに,どれほどの意義があるのだろうか?
クロピドグレルは,それ自体は薬効を有さないプロドラッグであり,クロピドグレルの薬効を担う活性体は,クロピドグレルの市場拡大後に発見された。人体がクロピドグレルの活性体を産生するまでには複数のチトクロームP450(CYP)のアイソザイムが関与するが,なかでもCYP2C19の寄与が相対的に大きいとされている。クロピドグレルの活性体を計測することは困難であるが,遺伝子解析は容易である。そこで,「クロピドグレルはプロドラッグである」「活性体の産生にはCYP2C19の役割が相対的に大きい」「CYP2C19によるクロピドグレル活性体の産生速度は遺伝子型により異なる」と論理を積み上げ,「クロピドグレル投与時の抗血小板効果,心血管イベント抑制効果はCYP2C19の遺伝子型により規定される」という証明されていない仮説をマーケット的に利用することにより,この遺伝子多型が注目されるに至った。
「CYP2C19の遺伝子型」に関する事実と「クロピドグレルによる心血管イベント発症予防効果」に関する事実は,1対1の関係にあるわけではない。酵素は触媒と同様に化学反応の速度を規定する因子であるため,「CYP2C19の遺伝子型」は「体内におけるクロピドグレル活性体の産生速度」とは相関するかもしれない。しかしクロピドグレルの活性体によるP2Y12阻害反応は可逆性の,速度の遅い反応である。したがって,クロピドグレルの活性体の産生速度と,薬効標的であるP2Y12占拠率の間の相関は乏しい可能性がある。また,ADP受容体にはP2Y12のほかにP2Y 1があることから,P2Y12阻害による抗血小板効果に個人差があることも想定される。さらに,心血管イベント発症に寄与するP2Y12阻害効果の個人差も大きいことが想定される。このマーケットストーリーともいえる「CYP2C19ストーリー」については,科学的仮説に基づいた検証を行う努力が必須である。
血栓イベントは複合的要因により影響を受けて発生する。「身体を構成する多数の遺伝子の多型の蓄積が個人差を規定する」という論理は部分的には真実であると考えられるが,長い歴史と世代を重ねた人類では,生存に都合の悪い遺伝子型はすでに歴史の過程において排除されており,現在生き残っている人類において単一遺伝子型による疾病発症,薬効発現への寄与度は小さいと想定される。
現在の遺伝子解析技術の進歩は個人のゲノム情報の集積を可能としつつある。すべてのゲノム情報と生活習慣などの情報を数値データベース化して,各因子の血栓イベントの発症への寄与度を算出できる日も遠くない。そのような時代を想像しても,単一遺伝子の多型が血栓イベントに寄与する割合が数パーセントを越えることはとても想像できない。現在の「CYP2C19ストーリー」は企業のマーケット戦略による科学的ノイズであるというのが筆者の一貫したスタンスである。