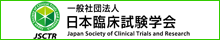THERAPEUTIC RESEARCH On-line
不完全な研究結果から導かれた誤った推論に過ぎない
糖尿病患者でがんの発症リスクが高いことは,複数の疫学研究で証明されている。近年,グラルギンなどの特定の糖尿病治療薬が発がんを促す可能性が指摘され,「グラルギン問題」と話題をよんだ。一方で,2012年6月に行われた米国糖尿病学会では,グラルギンと発がんの関連はみられないとするORIGIN試験の結果が発表された。これをもってグラルギン問題は収束したといえるのか。そもそもグラルギン問題の発端となった仮説とは何だったのか。ここでは,米国糖尿病教育プログラムの代表を務めるJohn Buse氏に,グラルギン問題について聞いた。
3種類以上の糖尿病治療薬が,がん発症リスクに関与していることを示唆するデータがすでに報告されています。とくに,2009年に発表された四つの薬剤疫学研究で,高用量グラルギンが発がんリスクを上昇させることが示唆され,「グラルギン問題」と話題をよびました。これに関係する論文は89件(うち51件はエディトリアルまたはコメンタリーとして発表)にも上ります。しかし,疫学的解析やRCTによるデータはわずか20件で,いずれも決定的な決め手に欠けるものでした。
「グラルギン問題」の発端となった薬剤疫学研究は,【1】インスリンアナログ製剤(グラルギン)はインスリンにくらべ,インスリン様成長因子1(IGF-1)の受容体と結合しやすい,【2】IGF-1は細胞成長を促進する作用をもつ,【3】ゆえにグラルギンは発がんを促進する,という間接的な推論を重ねた仮説を基盤としています。さらに,グラルギンは皮下注後,そのほとんどが代謝されてしまい,代謝産物には細胞成長を促進する作用がありません。ですから,「グラルギン問題」は,発端となった仮説自体に無理があるのです。
一方で,最近,欧州や米国で,多数の患者を対象とした質の高い後ろ向き解析が実施されましたが(Northern European Database Study,Kaiser-Permanente Cohort Study),グラルギンと発がんの関連は証明されませんでした。また,ランダム化比較試験であるORIGIN試験でも,関連は見いだされませんでした。
私の考えでは,特定の薬剤と発がんリスクにまつわる話題のほとんどは,不完全な研究結果から導かれた誤った推論だと思います。仮に特定の糖尿病治療薬が発がんと関連する可能性があるとしても,発がんリスクは1イベント/10000人・年増加する程度です。それに対し,心筋梗塞や脳卒中,あるいは死亡のリスクは年間で10%減少します。このリスクとベネフィットを考えると,われわれ医師は,HbA1cを低下させることに専念すべきだと考えます。私は,若年者であれば7%未満,余命が限られた高齢者では7.5~8%を目指すようにしています。
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 医学部 教授